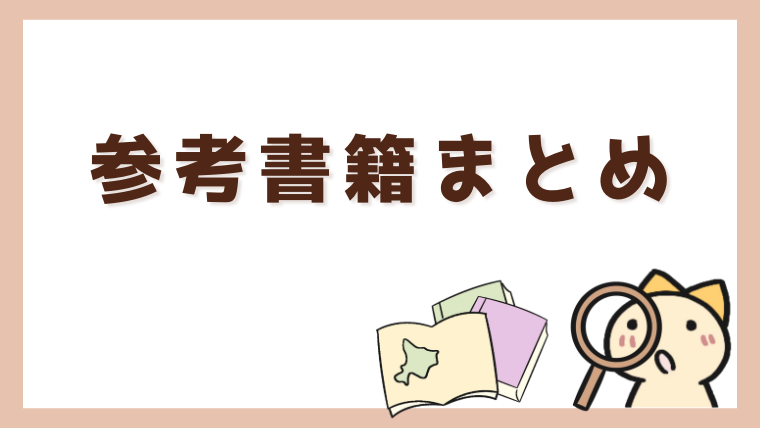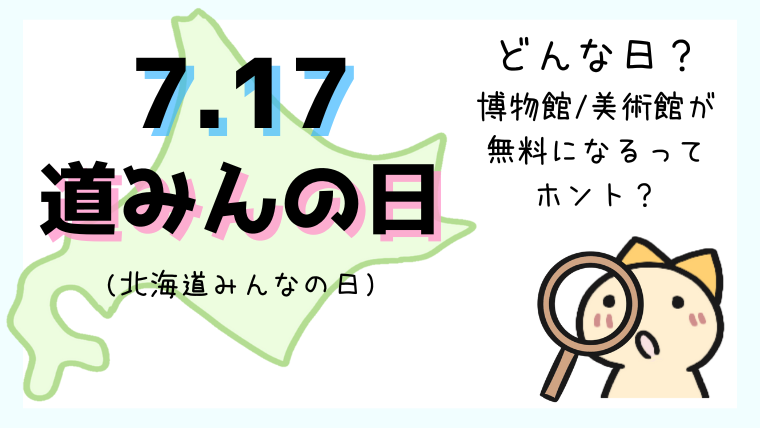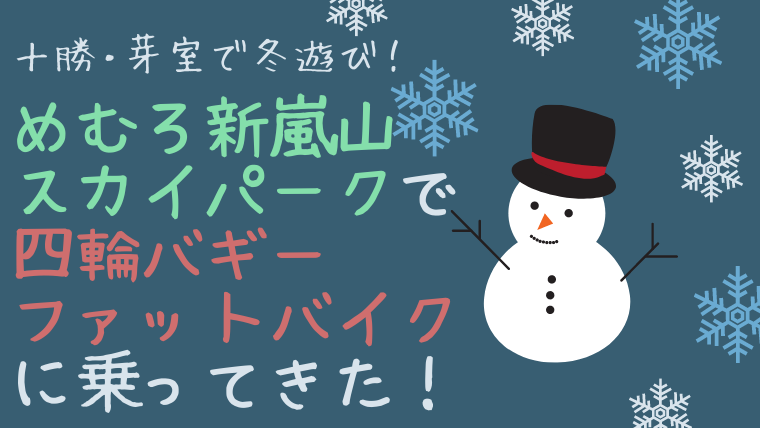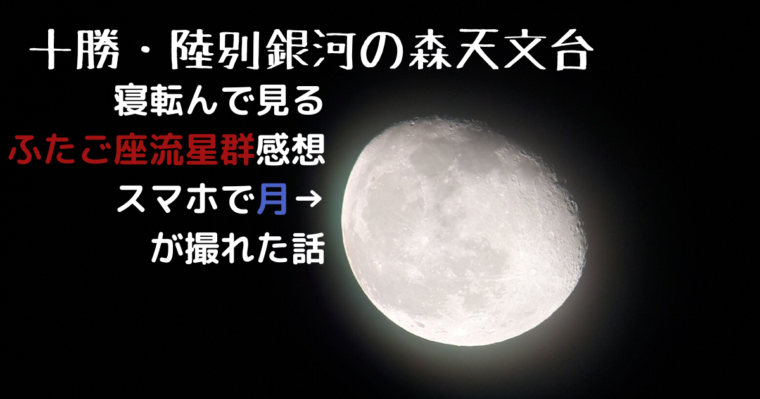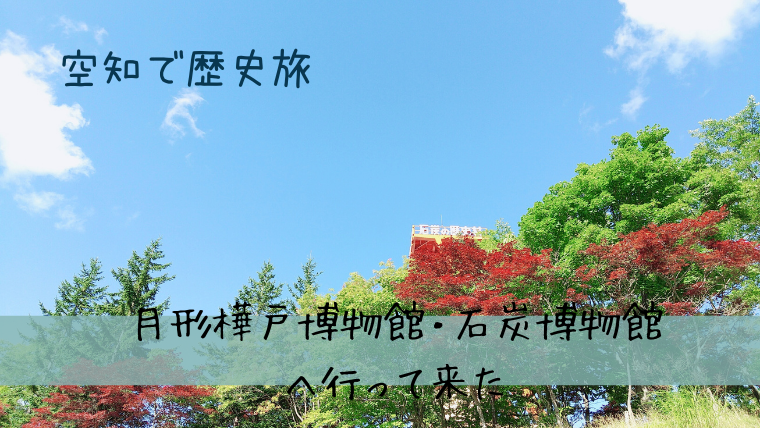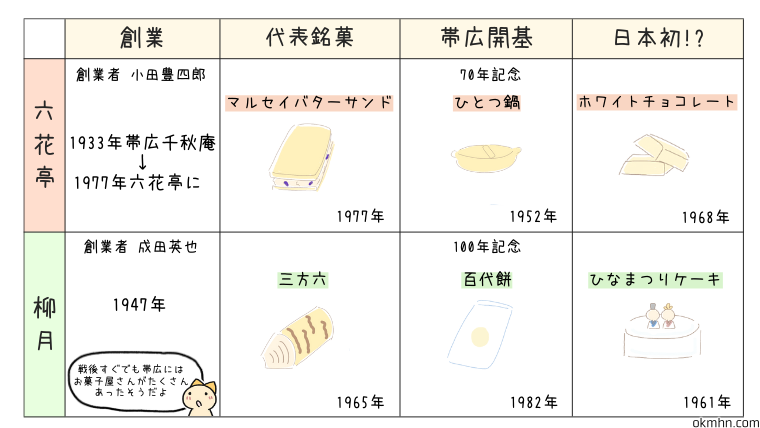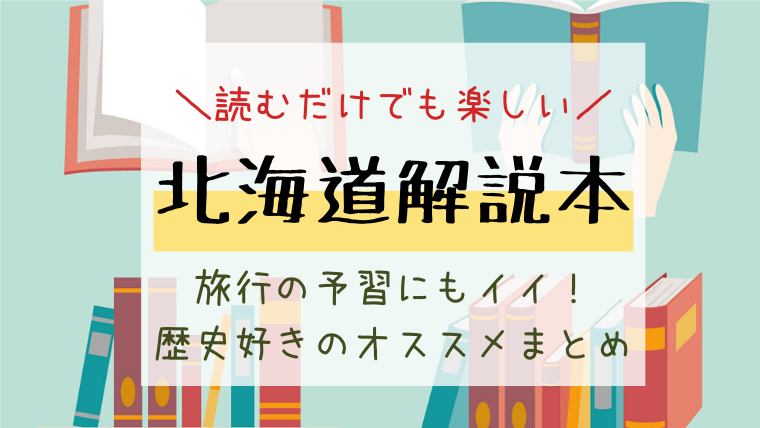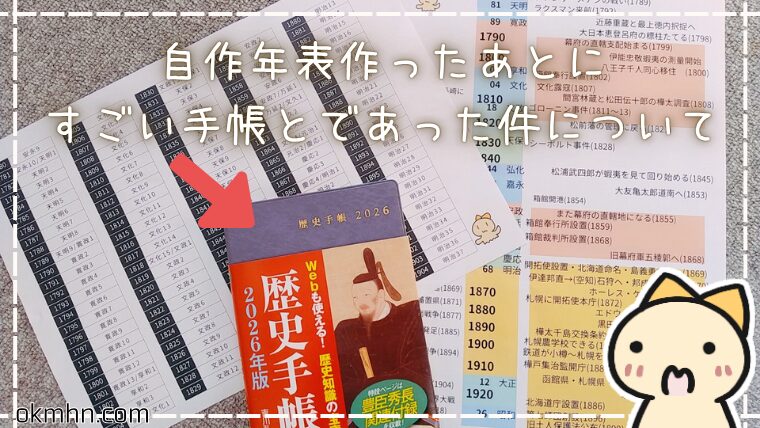北海道が好き!残酷で暗い歴史に触れて思うこと&受け止め方
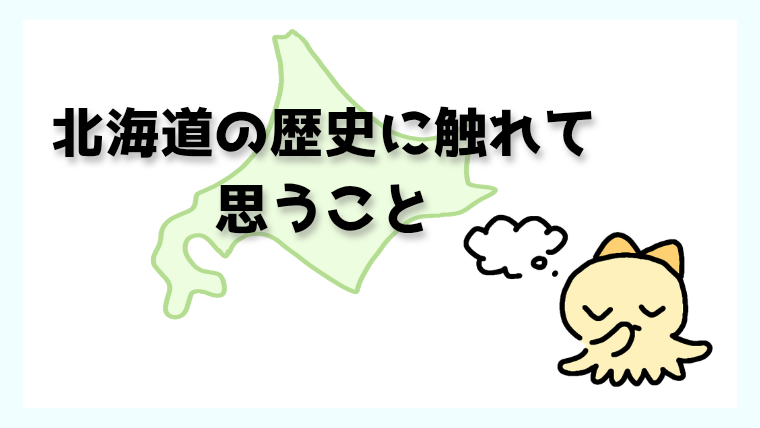
「自分はこの土地にいていいのだろうか」
そんな気持ちになった事はありませんか?
私自身、この問題とどう向き合えばいいのか、長い間悩んできました。
そして自分の子どもが生まれた事で、子たちには親として、どう伝えたら良いのかも考えるようになりました。
改めて先人たちの歴史を学ぶ中で、私は自分の中にあった問いに、私なりの答えを見つけました。
今回は、北海道の歴史が残酷で、暗く、悲しいものだと知ったとき、
自分はどう受け止めればいいのか、子どもにどう伝えていけばいいのか、を考えてまとめた話です。
私のルーツと立ち位置

祖父母の家は、父方も母方も北海道にあります。
私は長い間、自分を「北海道生まれ世代の二代目」だと感じてきました。
父方の曽祖父母は、会津藩に関係した出自で、明治の混乱期に北海道へ渡ってきた人たちです。
北海道の歴史、とくに明治期の開拓移住について調べる中で、
自分の家系もまた、その当事者の一部だったのだと理解するようになりました。
アイヌ文化への敬意と興味を持ちながら、
自分のルーツにも向き合い、誇りを持ちたい。
単純なものではなく、複合的な目線で北海道を理解したい。
それが、北海道に根を下ろしてきた四世代目としての、今の私の立ち位置です。
子どもの頃から抱えてきた違和感
改めて私の話になってしまうのですが。
小さいころから、本や郷土史の授業で「アイヌ民族は和人に迫害され、酷い扱いを受けてきた」という話にたくさん触れてきました。
日本の大筋の歴史には近世代になるまで北海道がほとんど出てこないし、日本の神話や古事記には北海道がほぼ出てきません。
そして、小学生の時に行った網走監獄博物館へのバス見学で見聞きした囚人の話。
北海道のなりたちは残酷で、冷たくて、暗い。
その延長線上に、今の自分がいる。
そうした話を重ねて受け取るうちに、自分のルーツをどこに置けばいいのか分からなくなっていました。
「和人=加害者」「本州ルーツの人間=加害者」というイメージが頭に刷り込まれ、自分もその加害者側なのだと感じるようになっていきました。
憧れと罪悪感のあいだで
それでも、アイヌ文化そのものへの興味が消えることはありませんでした。
民話や神話を読み、アイヌ語の言葉を覚え、地域のイベントで刺繍体験をしてみる。
知りたい、触れたいという気持ちは、ずっとありました。
けれど大人になるにつれて、
「この文化を壊した側に、自分と同じルーツの人たちがいる」
そう思うようになり、強い罪悪感を抱くようになりました。
アイヌをテーマにした番組を見ると、自分が責められているような気がして、最後まで見られないこともありました。
調べ続けて見えてきたこと

北海道の歴史や全体の流れを調べ続ける中で、少しずつ見えてきたことがあります。
明治以前から、本州とアイヌの人々のあいだには交易や交流があったこと。
アイヌの人々の中にも、和人の暮らしを取り入れながら、自分たちの文化を守ろうとした人がいたこと。
北海道の歴史は、単純な「加害/被害」の図式では語れない、複雑な積み重なりの上にある。
そう思うようになりました。
そして、北海道の暗く冷たい歴史は、
アイヌの人々だけに向けられていたものではなかったということも、改めて知ることになりました。
北海道を作った、たくさんの苦しみ
アイヌの人々の苦しみ
これは被害を否定したいという意味ではなく、
単純な一つの像に押し込めたくないという思いからです。
アイヌの人々についても、「ただ一方的に迫害された存在」としてだけ語ることには、私は違和感があります。
民話には争いの話もあれば、隣同士で折り合いをつけようとする話もある。
シャクシャインの戦いのように、抵抗の歴史もありました。
和人との関係も、すべてが敵対だったわけではありません。
交易があり、助け合いがあり、結婚や共同生活の例もありました。
もちろん、感染症や同化政策によって大きな被害や、悲しみを抱える事になったのも事実です。
ただ、その現実も含めて、「一様ではない姿」として捉えたいと思っています。
本州出身者など日本人の苦しみ
北海道の歴史の残酷さは、アイヌの人々への同化政策だけではありません。
江戸時代後期、蝦夷地警備を命じられ、寒さと飢えの中で命を落とした東北諸藩の藩士たち。
明治維新で敗れ、故郷を追われるように北海道へ渡った人々。
囚人やタコ部屋労働者によって築かれた道路や鉄道。
厳しい自然の中で苦悩しながら生きた開拓民たち。
それぞれが、それぞれの事情と苦しみを抱えながら、この土地に関わってきました。
誰が完全な加害者で、誰が完全な被害者なのか。
簡単には言えない歴史が、北海道にはあったのです。
「忘れてはいけない」という言葉の重さ
「こんな歴史があったことを忘れてはいけない」
この言葉は、北海道を語る歴史の中で様々な形で登場します。
私はこの言葉に、
「あなたたちは生まれながらにその業を背負っている」
と言われているように感じていました。
でも、子供をもった今、思うのです。
「忘れてはいけない」だけでは、その先が示されていません。
どう考え、どう生きるのか。
これまでの反省や悲しみを踏まえて、どうしていけばいいのかを考える。
そこまで含めてこそ、歴史は未来につながるものになるのではないでしょうか。
子どもたちに伝えたいこと

私は、子どもたちに「生まれた時から罪を背負っている」とは教えたくありません。
伝えたいのは、
「知って、考えて、自分なりの答えを持つこと」。
さまざまなルーツを持つ人たちが、それぞれの事情を抱えながらこの北海道に関わり、今につながっていること。
その複雑さを知ったうえで、未来をどう作るかを考えてほしいのです。
極端な言葉が生む分断
SNSなどで、こんな言葉を目にすることがあります。
「そんな歴史の果てに作られた道産のものを食べるな」
「アイヌの人に住まわせてもらっている自覚を持て」
こうした言葉は、一見すると正義のように見えるかもしれません。
でも実際には、誰かを救うためではなく、別の誰かを傷つけてしまうことがあります。
その反動として
「アイヌ民族はもういない」
「今のアイヌは偽物だ」
といった、別の極端な言説が生まれてしまうのだと思います。
北海道の歴史は、部分だけを切り取って語れるものではありません。
交流も、衝突も、移住の理由も、そのすべてを含めて見なければ、現実は見えてこないと思うのです。
終わりに・北海道は多面体
私は北海道を「多面体」だと思っています。
見る角度によって、困難の歴史も、協力の歴史も見える。
残酷さも、文化の交わりもある。
一つの正解で割り切れない。
この複雑さこそが、この土地の豊かさなのだと思っています。
歴史は、単純な決めつけでは語れません。
誰かを断罪するための道具でもありません。
私は、この複雑で、いびつで、完全ではない北海道を愛しています。
私の愛する故郷です。
だからこそ、思うのです。
歴史の区分を超えて、この多面体の北海道で生きる仲間として、共に未来を築いていく建設的な話し合いが生まれますように。
これからを生きる次世代が誇りを持って北海道で生きられるようになりますように。
これが、今の私の願いです。
長くなりましたが、この文章が同じような思いを抱える人々の心に届き、建設的な思考と知る事のきっかけになることを願っています。