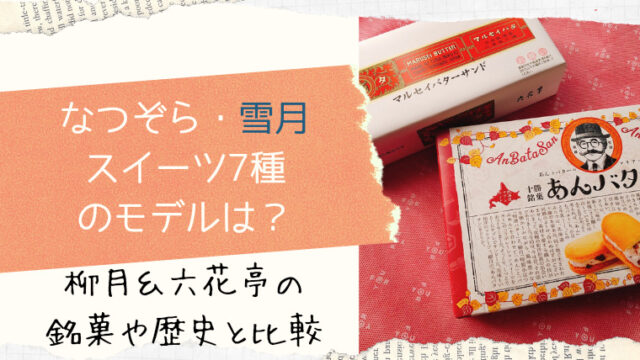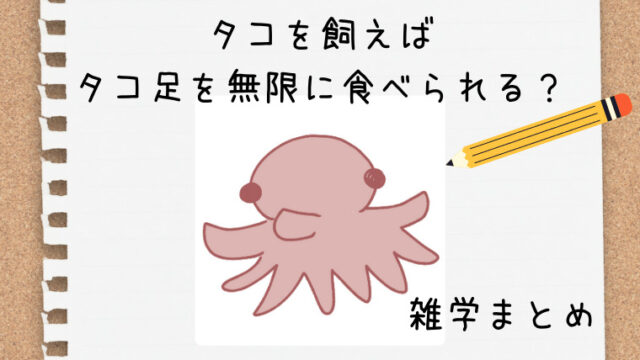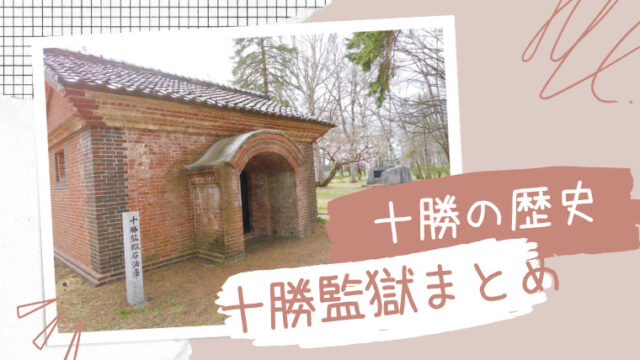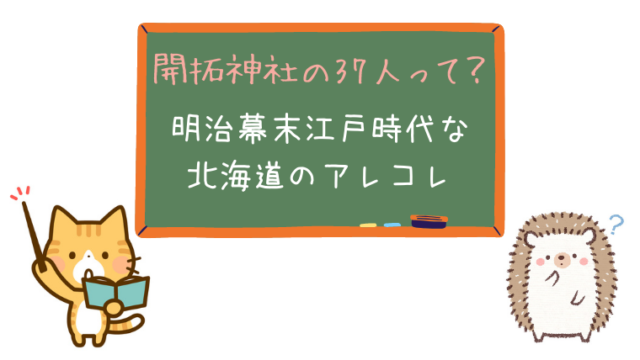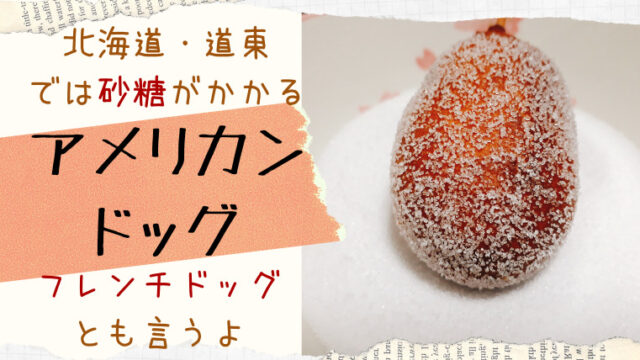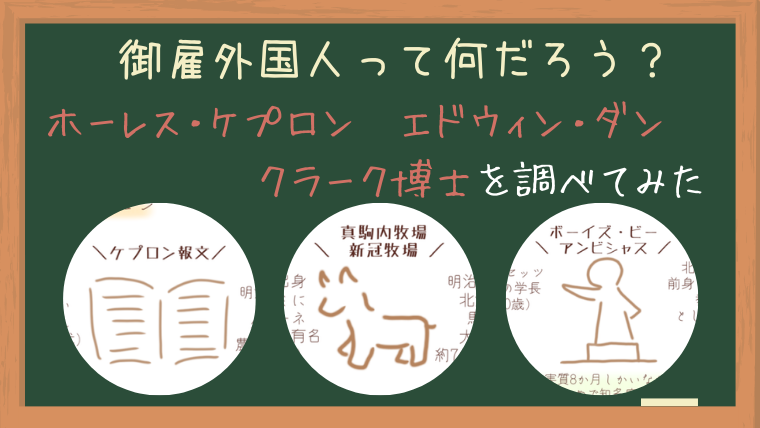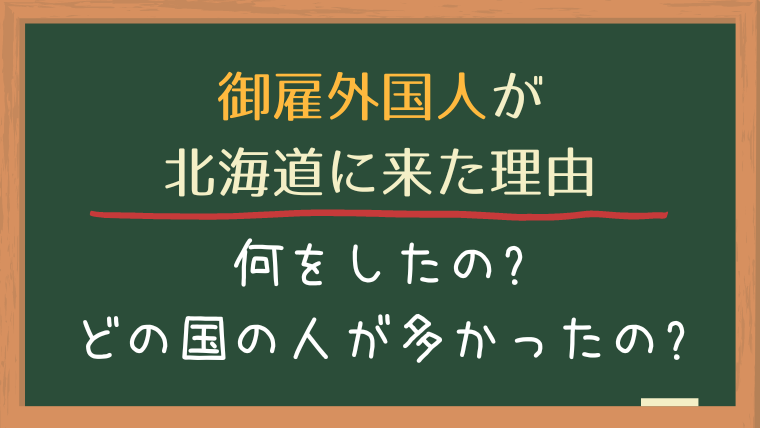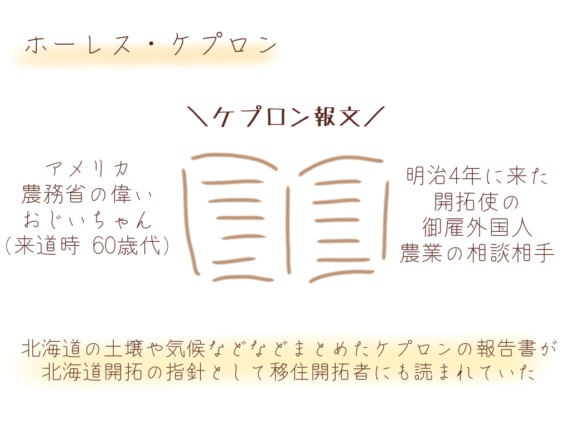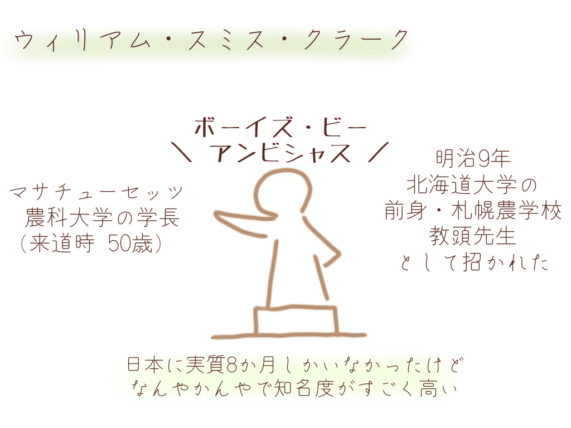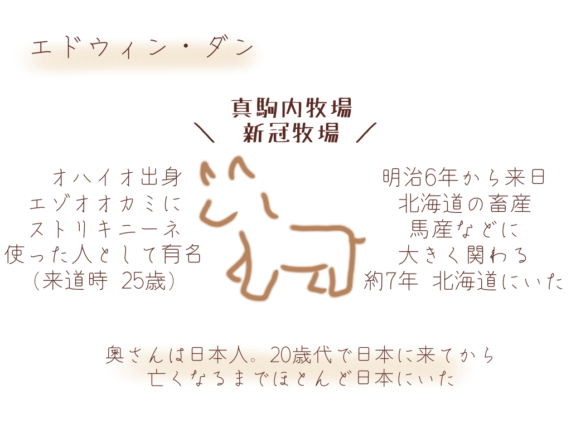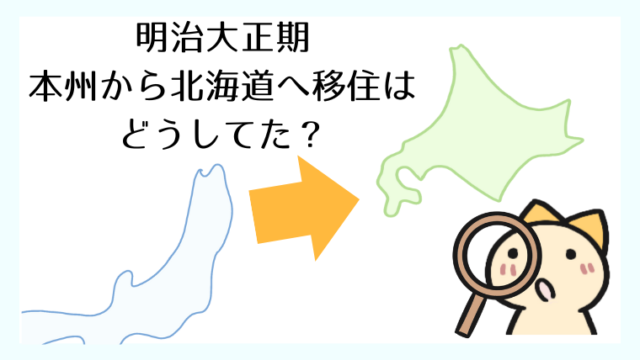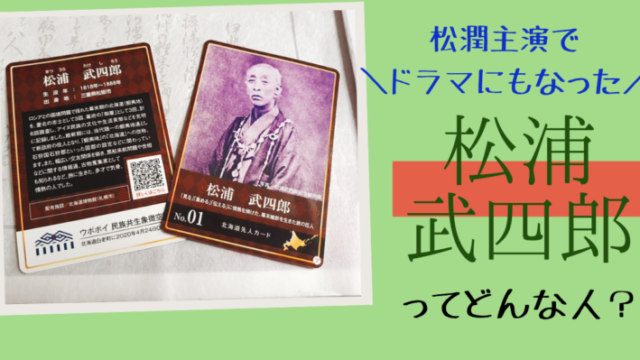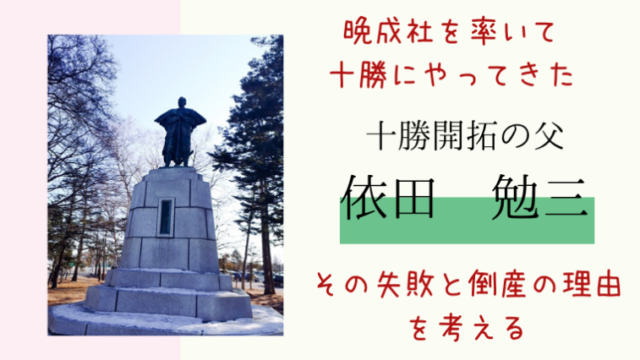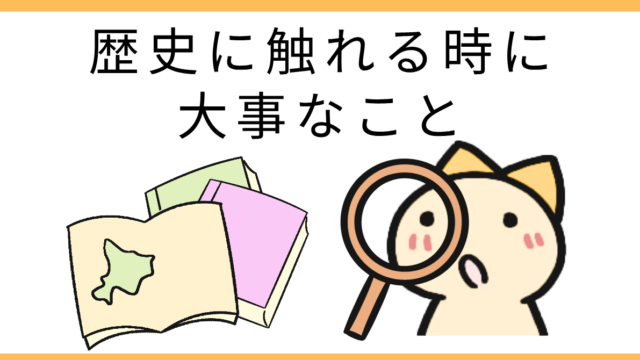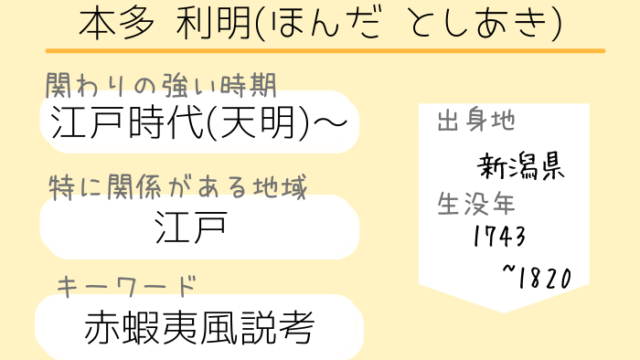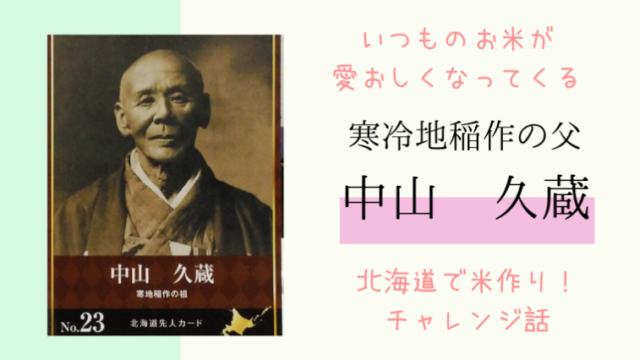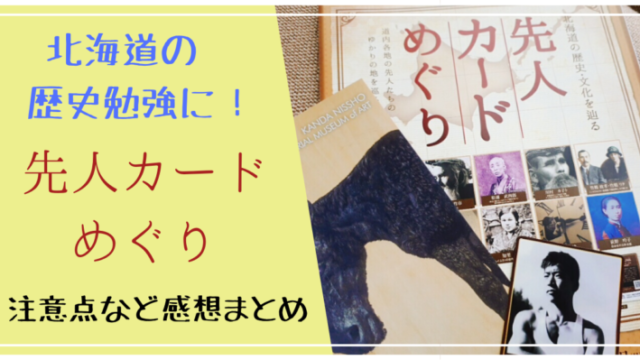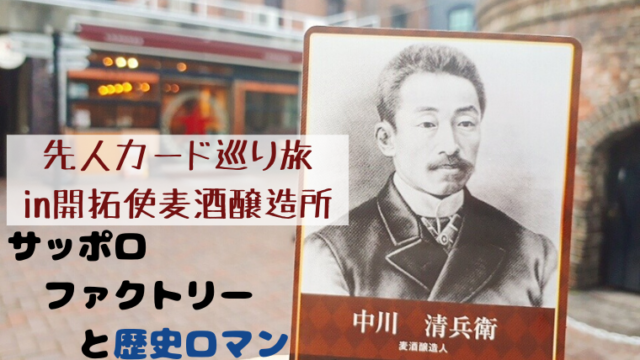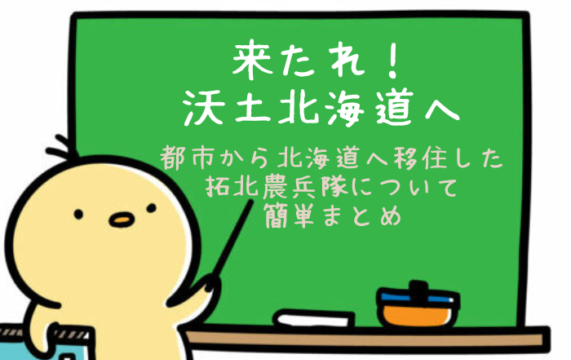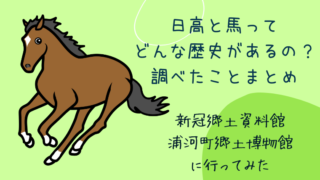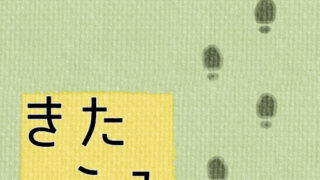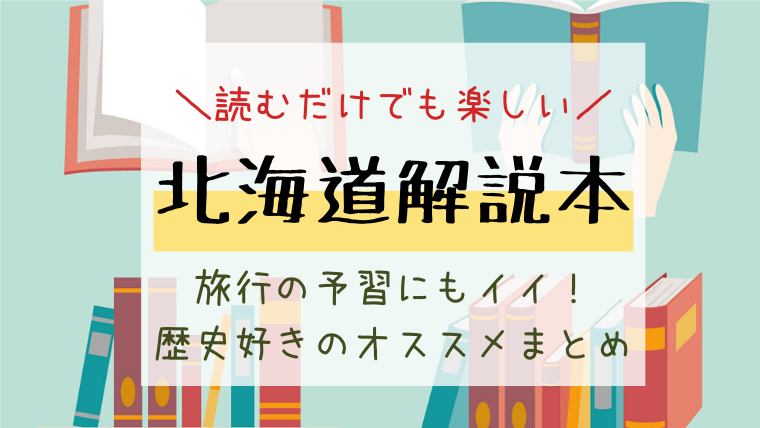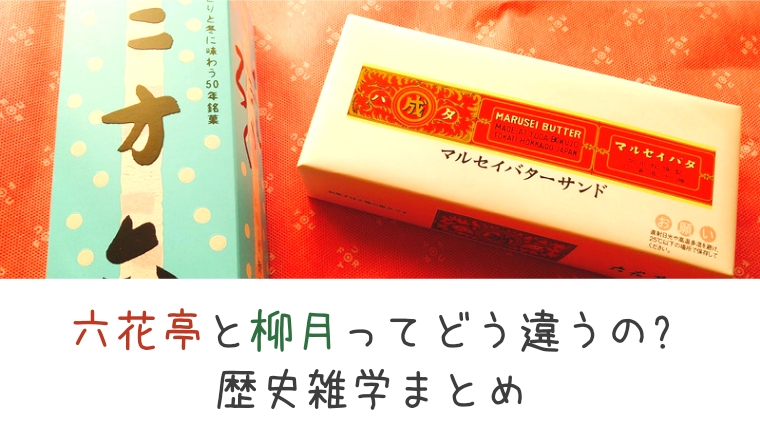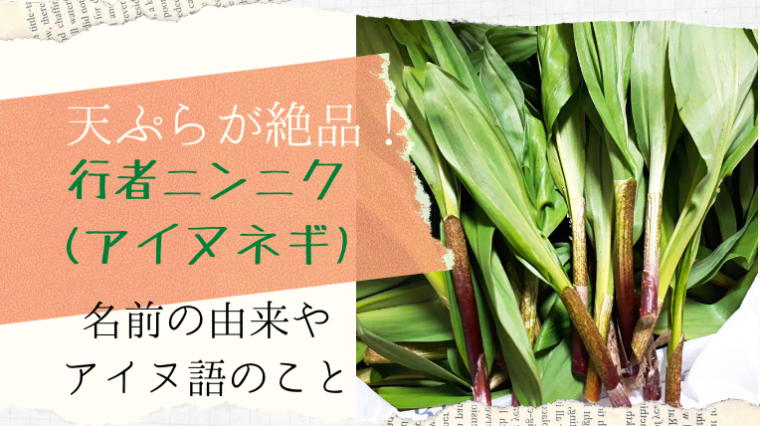明治時代に開拓使によって雇われた外国人の先生たち、御雇外国人(おやといがいこくじん)って知ってますか?
クラーク博士とか有名だよね
でも、実際どんな事してたの?
ボーイズ・ビー・アンビシャス!(青年よ大志を抱け!)って言うだけの人ではありません。
そして、クラーク博士よりも長く日本に滞在したり、北海道に滞在していた人たちもいます。
今回は明治開拓期な北海道の指針となった人々、
御雇外国人について特にホーレス・ケプロン、エドウィン・ダン、ウィリアム・スミス・クラーク(クラーク博士)の3人について
調べた事をまとめてみました。
なんで3人なのかというと、何かにつけて名前が出てくる人たちだからです。
※おかめ個人の体感
北海道内の博物館や歴史の話になると出てくる人なので、覚えておいて損は無いかと思います。
- 北海道の歴史に興味がある
- 博物館行ったらケプロンとか御雇外国人って書いてあって誰?ってなった
- クラーク博士って何した人なの?
- エドウィン・ダンも名前だけ聞いた事ある
- 北海道の観光・旅行で博物館に行きたいと思っている
という方の参考になれば幸いです。
御雇外国人について
御雇外国人は、開拓使が外国から招いた先生たちのことです。
アメリカの農務省にいた、ホーレス・ケプロンがその最初の1人だったとも言われています。
有名な御雇外国人3人
ホーレス・ケプロン
黒田清隆がアメリカに行って、来てほしいとお願いしたおじいちゃん。
ケプロン報文という北海道についてまとめた調査書が有名です。
詳しくはコチラをクリック↓↓
クラーク博士
札幌の羊ヶ丘展望台に銅像があったり、
ボーイズビーアンビシャスという言葉が有名なクラーク博士。
実は1年も北海道・日本に居なかったし、帰国後はちょっと切ない事になっていた人です。
詳しくはコチラをクリック↓↓
エドウィン・ダン
馬を愛し、エゾオオカミを退治した事で良くも悪くも有名な人です。
北海道酪農の父の1人で、ケプロン、クラーク博士と比べると人生の大半を北海道・日本で過ごしました。
詳しくはコチラをクリック↓↓
最後に
以上、御雇外国人って誰なのさ?何したのさ?についてまとめました。
あくまでも個人的にこの人達よく名前出て来るなーって感じている3人を簡単にまとめただけなので、本当はもっと色んな事をしていたり、色んな人がいたり。
もっと調べていくと、博物館に行ったり、北海道の歴史の本を読む度にすごく楽しくなる事間違いなしです。