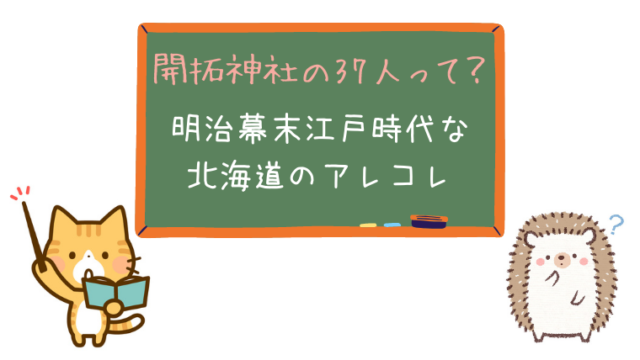六花亭の歴史って?有名なお菓子の誕生秘話まとめ
okamehan
きたうみ日誌
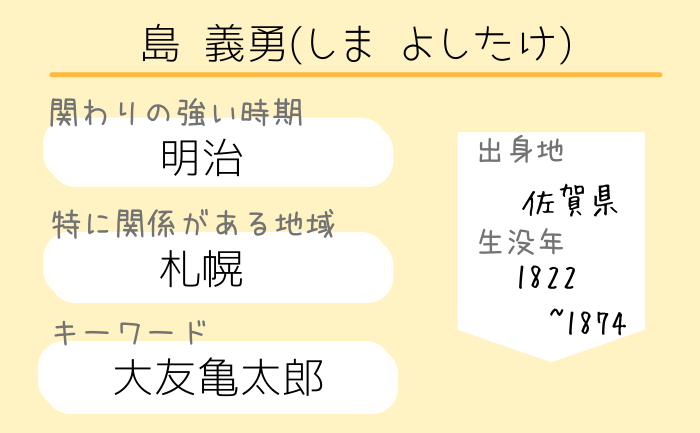
雪が降る季節に札幌で町作りを始めました。
計画が壮大&物資や食料が足りない&人手も足りない
そんな中で頑張っていたら北海道開拓の為の予算をすごい速さで使ってしまったので、箱館に赴任していた東久世がびっくり&激怒。
義勇を辞めさせるか、費用を増やせという話を上の人に話したら、義勇が辞める事になりました。
ただ、義勇が去った後に実際に東久世や岩村がその計画を引き継いだところ、壮大だけれどもちゃんとした計画だったので驚いたと言われています。
明治天皇から開拓の心のよりどころにと指示し、島義勇が背負って行った神様達です。
それぞれ、北海道の国土や開拓の精神、薬や酒造を司っています。
現在の北海道神宮に祀られている神様たちで、札幌の神社や帯廣神社など御分霊を祀っている神社も多くあります。
義勇の時には仮の社が作られ、1871(明治4)年には札幌神社と名前が決められ、現在の位置に移っています。
昭和39年に明治天皇を御祭神にお迎えしたので、北海道神宮に名前が変わりました。
大友堀と垂直になるように島によって大通りが作られ、札幌が碁盤の目になる基になったとのだとか。
1870(明治3)年には北海道を去っています。
明治政府のやり方に納得が出来なかった為、とも言われています。